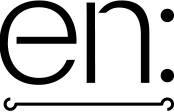まずは今回の展示のコンセプトについて教えてください。
なぜenという言葉にしたかというと、昨今の日本の建築状況は20~30年前とはかなり変わってきています。至極当然のことながら、建築を取り囲む社会状況がずいぶんと変わり、それに応じて建築もそのあり方を変えてきたわけです。
具体的にはどういうことでしょうか?
日本が成長をする社会ではなくなってきたということですね。高度成長期とは明らかに社会のあり方が変わってきていて、雇用状況の悪化や貧富の格差拡大というのはメディアがこのところ盛んに伝える通りです。非正規雇用の割合がいまや労働者の4割を超え、かつては日本を支えていると言われていた中間層の空洞化もこのところ劇的に進んでいる。そして少子化その他のさまざまな問題も抱えながら解決の糸口さえ見出せていない。こうした中で、以前と同様の仕事をしている建築家もまだ数多くいますが、ともあれ、社会の深刻な変化によって、前回のビエンナーレで提示された、1970年代を中心とするような、日本の過去の建築のあり方とは違ってきているということですね。
要するに、明治以来、日本という国家がつくり上げようとしてきた社会とは今や違う社会構造になってきたということだと思います。近代国家というのは、成長することを前提としてデザインがされてきたわけですが、そうではなくて、成長しなくなったこの社会の中で建築がどういう方向に行くのかを建築家は考えていかなくてはいけない。
たとえば、強度のある形態、オブジェクトを目指すような傾向が、21世紀に入ったあたりから徐々に薄まってきたような印象がありますが、これはいま話をされたようなことと連動していると言えますか?
たぶん、そうなんでしょうね。今回出展してもらう建築家たちの作品は、今のお話のような、作家性を前面に押し出したような建築というよりは、どちらかというと、一見アノニマスな印象を与えるものが多い。そのあたりが今回のenというコンセプトにつながってきます。
どういうことでしょうか?
enという言葉は、「関係性をつくる」という点に着目したところから出てきました。つまり、日本語の縁という言葉には“つながり”や“関係”という意味がありますが、今回の12組の建築家の作品には、つながりや関係を新たにつくっていこうという姿勢を見ることができる。でも関係というのは眼には見えない。そして、そのことによって彼らは、少し前までの、眼に見える形そのもの、形の強度のようなもので勝負しようというような建築家たちとは目指すところが変わってきていると言えるし、より豊かな包容力をもっていると言えるかもしれない。
建築というのはそもそもモノとか人とか社会との関係の中でつくられているわけですが、日本語の縁という言葉自体をコンセプトとしてすえることによって、社会のさまざまな関係性から社会が抱え込んでいるさまざまな問題までを浮き彫りにしていこうということ—これが今回の展覧会のストラテジーですが、さらに進んで、縁という言葉を、つながりや関係という視点に限定せずに、もっと広い視点、縁という言葉がもつ幅広い語義からとらえようということも考えています。
今回の12組の建築家は、70年代半ばから80年代半ば生まれの若い人たちが多いですね。
たまたま若い人の方が社会と建築の変化に対して敏感だったということだと思います。ただ、世代的なことに注目するよりも、成長することを前提にデザインがなされたのは70~80年代ごろまでで、その後、成長というものが難しくなったこの状況の中で、新しい世界を想定、イメージして何かを提案するということから、社会の中の個別の課題をとらえてそれに対して応えていくという方向へと建築がシフトしてきたという変化の方に注目した方がいいかと思います。
その方向に徐々にシフトしてきて、今になってその傾向が熟成してきたというかある程度まとまって浮上して見えてくるようになったということでしょうか?
開催まであと半年ちょっとですが、最後に開催に向けての抱負を聞かせてください。